
こんにちは、しょーゆ(@jiyuwotsukuru)です。
右肩上がりに株価が上昇する今、この10か月ほどで、私たちの世帯資産は約20%増加しました。
背景には、相場全体の好調と、非課税口座(新NISAや旧NISA・ジュニアNISA)を最大限に活用し、全世界株式を中心に長期投資を続けてきたことがあります。S&P500や日本株の力強い上昇の恩恵も受けることができました。
順調に見える今だからこそ、改めて「現状の整理」と「最悪のシナリオへの備え」を考える必要があると感じています。
もくじ
現状の整理
まず私たちは、生活防衛資金として世帯支出の約2年分を現金で確保しています。共働きで安定した給与所得があり、大きな借金(住宅ローンや車のローン)も一切ないため、かなり手厚く保守的なキャッシュポジションを持っています。
そのうえで、その他の資産はほとんどを全世界株式に、一部をコモディティ(貴金属)や暗号資産に投資しています。リスク資産の中でも分散を意識してはいますが、実態としては株式の比率が高いため、相場の影響を大きく受けるポートフォリオになっています。
最悪のシナリオを考える
最悪のシナリオは、やはり相場の暴落です。
全世界株式に連動する以上、特にS&P500の大幅な下落は避けられず、大きな資産減少に直面する可能性があります。
さらに私たちは、より自由な生き方を目指して「働く時間を減らす」「場合によっては働かない選択をする」ことも考えているため、収入が細るリスクと市場リスクが重なると厳しい局面になりかねません。
最悪のシナリオを数値で考える — 米国株の割高感と大暴落の可能性
今のS&P500は、長期的なバリュエーション指標であるShiller CAPE(Cyclically Adjusted PE)が約37〜39と、長期平均(約31)より高めの水準にあります。これは「割高感」を示すひとつのシグナルであり、短期的な調整リスクがゼロではない状況です。
過去の大暴落と下落率・回復年数の目安
歴史を振り返ると、S&P500は何度も大きな下落を経験してきました。主なケースをまとめると次の通りです。
- 平均的なベア相場:下落幅はおよそ**−33%、回復まで2〜3年程度**が一般的。
- ITバブル崩壊(2000〜2002):S&P500は約−49%の下落、回復には約6〜7年かかりました。
- リーマンショック(2007〜2009):S&P500は約−50〜57%下落、回復には約5〜6年。
- コロナ急落(2020年):S&P500は約−34%の下落でしたが、各国の金融緩和で半年ほどで回復しました。
- 大恐慌(1930年代):ピークから**−80%以上下落し、回復には20年以上**を要した歴史的最悪例です。
株式比率80%のポートフォリオで試算した下落インパクト
ポートフォリオは「株式比率80%、残りは現金やコモディティ」という想定です。
この前提で上記の下落シナリオを当てはめると次のようになります。
| 想定シナリオ | 株式の下落率 | ポートフォリオ全体の目減り幅 | 回復期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 平均的ベア相場 | −33% | −26% | 約2〜3年 |
| ITバブル/リーマン級 | −50% | −40% | 約5〜7年 |
| 大恐慌級 | −80% | −64% | 20年以上 |
ここから導ける実務的な備え
- 生活防衛資金の価値
世帯支出の2年分を現金で確保していることは大きな安心材料です。暴落時も取り崩さずに耐えられる心理的余裕があるのは強みです。 - 暴落は買い場にもなる
長期で見れば、暴落後は回復してきた歴史があります。むしろ追加で投資できる資金を持っている人にとっては「チャンス」でもあります。 - 働く期間を柔軟に考える
資産が一時的に減ったとしても、「収入を少しでも続ける」選択肢を持つことで、資産取り崩しの速度を遅らせることができます。フルタイムではなく柔軟な働き方でも十分な効果があります。
おわりに
資産が増えている今は、自分の投資判断を肯定的に捉えやすい時期でもあります。
しかし長期投資において大切なのは、順調なときの心地よさではなく、厳しい局面をどう耐え抜くか。
最悪のシナリオをシミュレーションしながら、自由な暮らしを目指す働き方と資産形成のバランスを考えていきたいと思います。

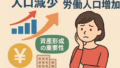

コメント